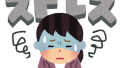超ブログ管理人のmanokanです。
今回も心理学に基づき【対人関係】をテーマに記事を書いていきます。
<(_ _)>どうぞ最後までお付き合いください
仕事をしていく上では、失敗はつきものです。
とはいうものの、失敗をしたいと思う人はいないでしょう。
では、失敗をしたときどうしますか?
たとえば、ある仕事の企画を立案するとします。
ところが努力をしたにも関わらず、他の人の企画が採用になった場合、失敗を受け入れられない人は、「どうせ採算のとれない企画だから、やっても損だ」と言い訳をする傾向にあります。
このように目標達成できなかった現実を「どうせ損をする」と、自分の責任ではなく、自分にとって都合のいいように解釈します。
それによって「採用されなかった」という自尊心を傷つけないようにしているのです。
この心理をフロイトは防衛機制のひとつの合理化と呼びました。
たしかに、心の負担を軽くするには有効かもしれませんが、失敗を受け入れずに周りの責任としていては、いつまでたっても成長しません。
失敗の原因を突き詰めて、再び挑戦を繰り返していくことで人は成長していきます。
だからこそ、「できなかった」という現実を受け入れて、次へとつなげていくことが大切になってくるのです。
フロイトは、イソップ物語の「酸っぱいブドウ」を引用して防衛機制の合理化の例としたことから、「酸っぱいブドウの理論」と名付けました。
イソップ物語「酸っぱいブドウ」
①ある日、キツネがおいしそうなブドウがなっているのを見つけた。しかし、高い所になっていたため飛び上がってとろうとするが、全く届かない。
②怒りと悔しさから、キツネは「どうせあのブドウは酸っぱくてまずいから、食べても損をするだけだ。誰が食べてやるものか」と言い捨てる。
つまり、手に入れたくてたまらない目的(欲求)を達成できなかったとき、自尊心を傷つけないように、自分に都合のいい理屈で埋め合わせようとする心理メカニズム。
「酸っぱいブドウの理論」と同じく、合理化のひとつに、「甘いレモンの理論」というのもあります。
たとえば、テストであまりいい点数をとれなかったけれど、「あのテストは難しいから50点とれたことは素晴らしいこと」と自分自身を過大評価してあげるのです。どちらも現実を受け入れずに、自分の都合のいい理屈でもって自尊心を傷つけないようにしています。
◎失敗を受け入れず、自分以外の責任にして都合よくするのは傷つきたくないから
◎現実を受け入れることが成長につながる
<(_ _)>お読みいただきありがとうございました。
次回の記事はこちら→ 自信過剰な人とのコミュニケーションのとり方
前回の記事はこちら→ 自己評価は低いよりも高い方が絶対にいい!!